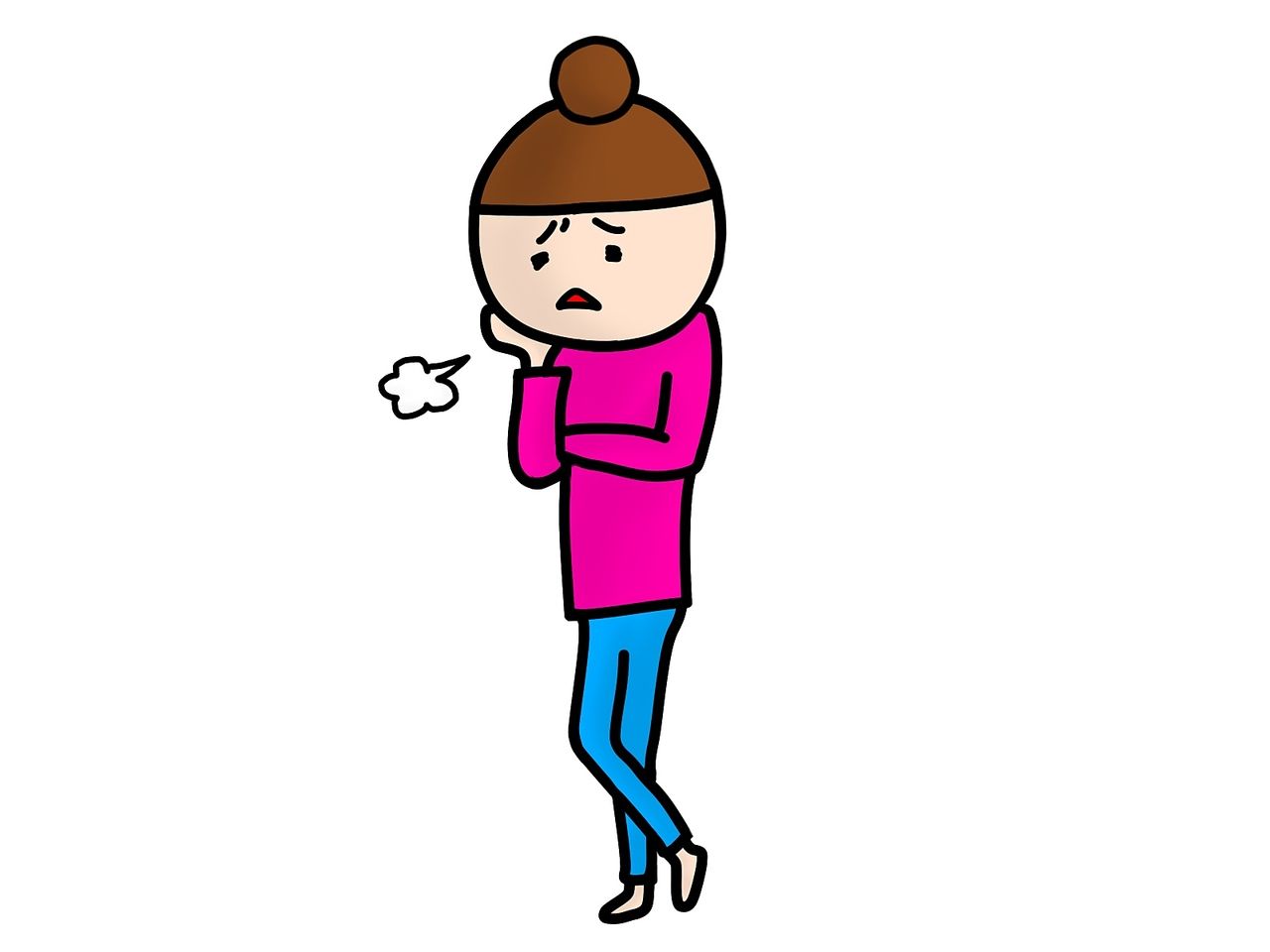超高齢化社会の「老老相続」という問題
厚生労働省が発表している2024年の日本人のの平均寿命は
男性 81.09歳 女性87.14歳 です
高齢化が進む一方、亡くなる高齢者も増え、相続の件数も増えています。
令和22年までは死亡者数は増加傾向にあると推計されていますので、これから年々、
相続件数が増えていきます。
超高齢化社会は、子世代も、相続が発生した時には高齢者になっており、相続時に様々な問題が起こっています。
相続人が認知症という問題
超高齢化社会になり、被相続人(亡くなった方)の配偶者が認知症になっていたり、相続人の子供の一人が認知症を発症している場合、スムーズな遺産分割協議ができません。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
相続人の一人が認知症で著しく判断能力が低下している場合は、遺産分割協議を行うことができないため、成年後見制度を利用して、成年後見人を選任して遺産分割協議を進めることになります。
成年後見制度は時間がかかる
家庭裁判所に申し立てを行ってから、審判が出るまでに2ケ月~4ヶ月程度は時間がかかります。審判が下りてから後見が開始されます。
成年後見制度で相続税の申告期限はどうなるのか?
認知症を発生している相続人は、後見人選任の翌日から10ケ月以内が相続税の申告期限
他の相続人は、相続を知った日の翌日から10ケ月以内が相続税の申告、納付期限
それぞれ、申告の期日が異なるので注意しなければなりません。
成年後見人はめんどくさい
成年後見人になると、とにかくめんどくさいです。
財産目録作成や定期的な家庭裁判所への報告、相続税申告書の作成など、事務手続きが大変です。
そして原則的に被後見人が死亡するまでやめられないということです。
最近は、後見人の横領リスクから、弁護士や司法書士を選任するケースが増えており、報酬料(2~4万円/月額)が発生します。
被後見人が亡くなるまで成年後見人の解任が認められないため、後見期間が長期間になると、被後見人の財産から支払われるので、相続した財産がかなり減ってしまうという問題もあります。
家族の事情を加味したいなら公正証書遺言を作成する
成年後見人は被後見人の不利になるようなことはできないため、法定相続分を主張します。このため、家族の事情を酌んだ遺産分割協議はできなくなります。
被相続人が生前に遺留分を考慮した公正証書遺言を作成しておけば、基本的に遺産分割協議書は必要なく、相続開始後に遺言書通りに遺産を相続することが可能になります。

関連した記事を読む
- 2025/05/31
- 2025/04/26
- 2025/04/15
- 2025/04/15