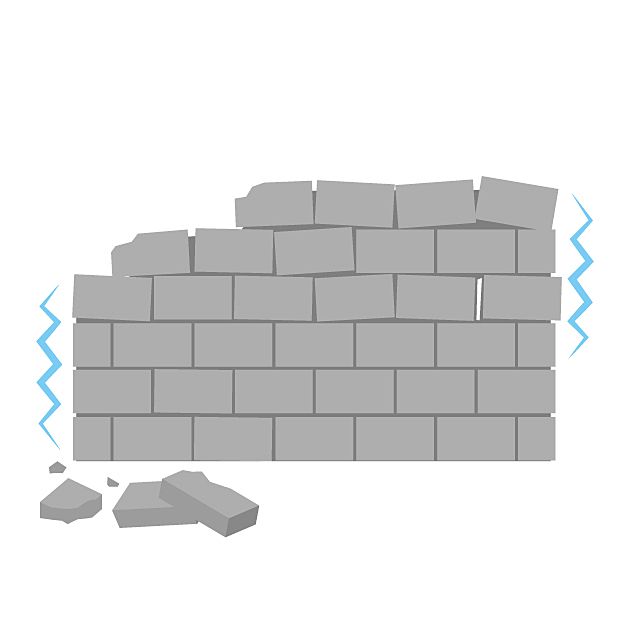ブロック擁壁には注意を!!
土地を購入する場合、道路より高く、隣地より高い土地を購入したいとお考えになりますよね。
もちろん、その通りなのですが、土留めには費用がかかります。既存のブロック擁壁が有った場合、ラッキーと思うかもしれませんが、再建築の際は土留めとして認められない場合がありますのでご注意ください。
法規制
●建築基準法は、高さが2mを超える擁壁は工作物として扱いますので、工作物として建築確認申請を提出して確認を受けなければ工事をすることができません。
●宅地造成等規制法では、規制区域内で1m以上の盛土又は2m以上の切土を行う造成工事を行う場合、工事の許可を得なければならないとしています。
上記の場合は基準に適合した擁壁を築造しますので、構造的な問題はありません。
ところが、宅地造成等規制法は、刈谷市・知立市・安城市ではほぼ定められてている場所はありません。
したがいまして、2m以下の土留めは申請等の義務がありませんから、施工業者の考えで土留めとしてブロックが使われてきた現場が多々存在します。
その中には、危険な現場も存在し、再建築の際には設計士が安全な既存擁壁としては認めてくれず擁壁工事をやり直す必要があります。
この場合、多大な費用がかかるだけでなく、建物の配置計画にも支障が出る場合があります。
土地取引の際、確認申請を要しない既存擁壁については、その安全性について不動産業者には説明義務はありませんし、実際わかりません。
安全性については専門家である設計士の判断になりますので注意してくださいね。
問題点
ちなみに、写真のブロック擁壁は見かけ高さが1.6mあります。厚みは15㎝で水抜き穴はしっかり設置されています。
しかし、今では、このブロックがCP型枠ブロック等でなかった場合、再建築する場合は設計士はOKを出しません。
設計士が安全と見做してくれない場合は、ブロックに建物の土圧をかけるわけにはいかないので、建物の配置計画に影響が出てしまいます。
既存ブロックの取扱いについては、各ハウスメーカーより見解が違い、土留め高さが1m以内(5段以内)であればOKを出すハウスメーカーもあるようです。
また、行政によっては、新規に確認申請を出す場合、ブロックの土留め高さを規制しているところもありますので、必ず確認が必要です。(40㎝以内等)
全国建築コンクリートブロック工業会でも建築用空洞ブロックの土留めとしての利用は2段までを推奨しています。その理由としては、土圧に耐えられる構造ではない事、耐水性がない事、中の鉄筋がさびて酸性化し劣化してしまう事があげられています。
そもそも、建築用空洞ブロックはブロック塀として利用するべき物なのですが、現実的には土留めと塀を兼ねている現場が多いのが実情です。
既存の擁壁がある土地、隣地が高くて擁壁がある土地を購入する場合は、必ず設計士に相談しましょう!!
最後に、下の写真は、弊社の現場で工事中のCP型枠ブロックの土留めの基礎配筋の写真です。
D13を@200で入れています。ブロック塀の基礎配筋とはまるで違います。それだけ土留めは頑丈に作る必要があると言うことです。

関連した記事を読む
- 2024/10/14
- 2023/06/04
- 2023/01/16
- 2023/01/10